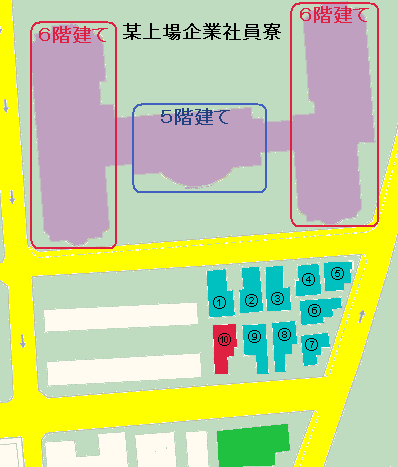
地上デジタル奮闘記 その3
私はこれまで我が家の地デジ奮闘のことばかり書いていましたが、電波障害で2002年に共に戦った近所の方々がどうしていたのでしょうか。これが驚く程動きがなかったです。私の地デジ奮闘が始まった2005年、室内アンテナで何とか視聴可能になった2006年頃は勿論、昨年2009年4月のUHFアンテナ設置を行った後も動きがありませんでした。さすがにUHFアンテナ設置をしたら、誰かが気がついて相談に来るかなと思っていました。その際はこれまでの苦労をお話しして、地デジ視聴に全面的に協力しようと思っていたのですが、誰も相談どころか、状況伺いにすら来ません。
つくづくみんな遅れているんだなと思いました。私が進み過ぎているとは思わないのですが。
そんな折、2009年9月頃やっと動きがありました。このあたりで地上デジタル電波の受信状況を検査するという内容が回覧されました。当然我が家はもはやどうでもいいのですが、結果には興味がありました。
それから2週間後くらいたった10月5日、結果についても回覧があり、10棟ともブースターを使用すれば視聴可能という診断結果でした。実はこの結果には少々驚きました。10棟の中では我が家は一番東京タワーに対して、電波障害建物のかぶり方がゆるい方だったのですが、それでも我が家の周辺6棟は何とか視聴可能だろうと予測していました。しかし残りの4棟は建物のかぶり方が激しいので無理ではないかと予測していました。改めて位置関係を図示します。
[地図3]
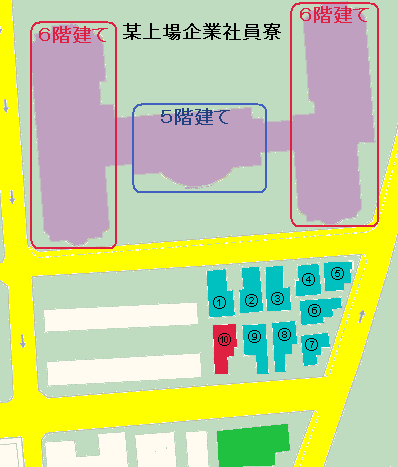
地図をみて頂くと分かるとおり、我が家(10号棟)をはじめ1、2、3、及び9、8号棟の6棟は東京タワー側(図では真上)の電波障害建築物は5階建てで、かつ距離が離れています。一方4、5、6、7号棟は6階建ての建物が、ぐっと近くまで迫っています。この位置関係や障害建物の高さの違いは微妙に、いやかなり受信可否に影響すると考えていました。
しかし結果は全棟OKということで、デジタルの耐電波障害性の高さを実感しました。
両親部屋はまだ一応ハイビジョンではあるもののフルハイビジョンには程遠いブラウン管テレビでしたが、ハイビジョン液晶テレビを買ってあげることにしました。エコポイントが使える間に買ってしまおうという目論見もあります。選んだのはやはり東芝REGZA(42Z9000)です。
両親にとってレコーダでの録画はどうしても難しいようで、その点REGZAであればテレビで録画する感覚で録画ができるので、これなら両親でも自分で録画ができるだろうと考えたからです。
[2台目ハイビジョン液晶テレビ 東芝
REGZA 42Z9000 (2010年1月25日配送)]

両親部屋は六畳間なので、リビングの52インチ(REGZA 52Z3500)と同じではさすがに大きすぎるので、42インチを選択しました。しかし52Z3500購入から2年がたっているので、機能面ではやはり進化しています。52Z3500と比べた進化点は以下です。
特にレグザダビング機能には私自身が非常に興味があり、すぐにはDLNAサーバは用意しませんでしたが、その準備として両親部屋にも有線LANを敷設する工事をしました。これには35,000円かかりました。
ちなみにREGZAを選んだ最大の目的はUSBハードディスクへの録画なのですが、やはりREGZA購入者の殆どが買うようなので、現在は量販店がサービスでハードディスクを付ける場合が一般的です。今回池袋のヤマダ電機LABI総本店で購入(1/23)したのですが、やはり以下のものをサービスでつけてもらいました。
[外付けUSBハードディスク バッファロー HD-CL500U2]
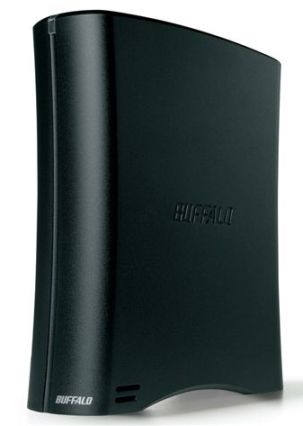
さて今回両親部屋への液晶テレビ購入により、今まで使っていたブラウン管ハイビジョンテレビは2階の子供部屋へお下がりすることとなりました。これにあたって私が一番悩んだのが、60kg以上あるブラウン管テレビをどうやって2階に上げるかでした。最初の購入時点は2階に設置したのですが、配送業者に上げてもらいました。その後1階の両親部屋に下ろすのは自分でやったのですが、非常に大変で階段を傷つけてしまいました。今度は下ろすのではなく、また2階に上げないといけません。
頑張って自分で上げるか、弟にでも手伝ってもらうか。一応業者にテレビ2階上げ作業を単独で実施する場合の見積もりをとったのですが、1万円から1万5千円くらいします。決して安くはないですが、しかたないかなと思っていました。
もうひとつの方法として、今回の液晶テレビ購入にあたり、当該テレビの配送、設置は無料サービスだったのですが、これに既存テレビの引き取り追加作業のイメージでオプションでお願いすることです。テレビ購入時にヤマダ電機で確認したところ、ちゃんとオプションが存在しており、何とたったの2,600円でやってくれるとのことでしたので、迷わずお願いしました。
今回の購入で我が家も3部屋が地デジ対応となり、一応基本的にはアナログ環境が必要なくなったので配線も整理しました。アナログが完全撤廃できている訳ではないし、まだアナログ放送をしているので、必要になる場面(コピー制御のない録画をするためなど)も皆無ではないと考え、一応アナログ視聴も可能な配線としています。
[配線図 3部屋地デジ化後の配線]
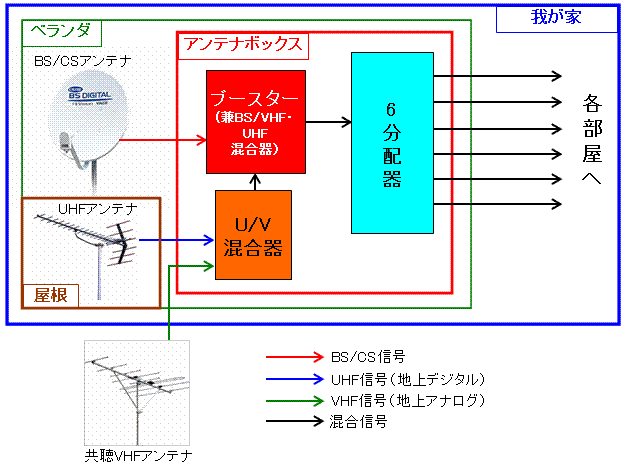
[3部屋地デジ化後のアンテナボックス]

ところで2階の子供部屋に上げたハイビジョンブラウン管テレビのチューナはアナログしかなかったので、SHARPのハイビジョンレコーダDV-HRD30をチューナー代わりにしていたことは以前も述べました。つまりセットでハイビジョン視聴を実現しているので切り離せない訳です。両親部屋に購入したREGZAは前述のようにUSB-HDDへの録画機能があり、またDVDプレーヤは別にあったので、基本的にはハイビジョンレコーダは必要ないのですが、このレコーダには両親が好きなコンテンツが録画されていたので、依然両親部屋に置いておくことにしました。その好きなコンテンツとはNHKで放送された「ムツばあさん」シリーズと子供(両親からすると孫ですが)の成長記録をビデオカメラからダビングしたものです。これらのコンテンツはUSB-HDDに移動させることはできないので、これらを引き続き視るにはこのレコーダを残しておく他ありません。
では子供部屋のハイビジョンブラウン管テレビはどうするか。昔のように内蔵アナログチューナでアナログ放送を視聴するか。しかしこれは非常に勿体無いし、3部屋地デジ化が完遂しません。別途安い簡易地デジチューナでも買うか考えましたが、姉の家に壊れたと言っていたハイビジョンレコーダがあることを思い出しました。どういう壊れ方なのか詳しく聞いていませんでしたが、この際チューナーだけでも使えたら御の字と考え確認しました。
すると録画済みデータの編集ができなくなっただけということで、チューナー視聴は勿論内蔵ハードディスクへの録画もDVDへのダビングも問題ないということでしたので早速貰ってきました。 PioneerのDVR-DT70という2006年製のハイビジョンレコーダです。
[姉からもらったハイビジョンレコーダ Pioneer
DVR-DT70]

2006年製で、シングルチューナー、ハードディスク容量も250GBしかなく、勿論Bru-rayでもなく、今となっては時代遅れのものですが、DV-HRD30の代替としては機能は全く同等、少なくともチューナー代わりとしては十分過ぎるくらいの性能なので全く問題ありません。これで何とか3部屋地デジ化が完了しました。
前述した昨年(2009年)の近所の受信状況検査後、それを進めていた加○さんも含め、実際アンテナが立つ様子はなかったのですが、やっと今年2010年2月頃から、ぼちぼち立ち始めました。そして3月頃までには3件が立てました。
[近所の地デジアンテナ設置状況
(クリックすると拡大します)]

上記写真は障害建物(某上場企業社員寮)をバックに(東京タワー方面に向けて)、真南からそれぞれ3件の地デジアンテナ設置状況が分かるように撮影したものです。
面白いのは、それぞれのアンテナの向きです。向かって一番左は8号棟の根○さんですが、方角的にはほぼ真西、東京タワー方向からみると90度西に向いています。真ん中は7号棟、昨年の受信状況検査を推進した加○さん宅ですが、方角的には北北西、東京タワー方向からすると30度ほど西向きです。そして向かって右は6号棟の○田さん宅ですが、高く、そして近くに立ちはだかる障害建物にもろに向けて真北に向けています。
いずれの方にも設置方法、その方向の決定理由などは伺ってないですが、恐らく反射波、回折波などを利用するにあたり、最適な方向を模索した上でのことだと思います。しかし疑問がでる方向にしている方が多いですね。再び位置関係が分かるよう地図を見て下さい。
[地図4]
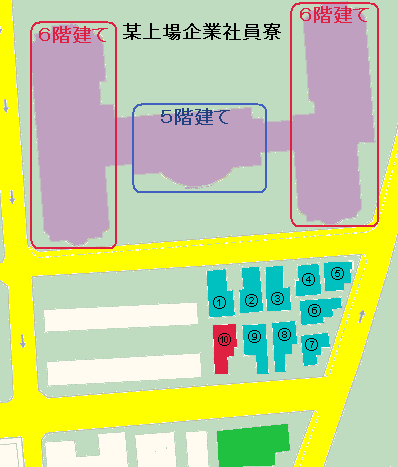
7号棟の加○さんが北北西向けに設置したのは、よく理解できます。近くに迫った6階建ての建物を避けた典型的な回折波利用だと思われます。
8号棟と6号棟は少々不可解です。特に8号棟は我が家と同じように障害建物の5階建て部分を越えるように高く設置すれば、東京タワーからの直接波も受信できるはずですが、完全に横を向いた形です。この方向からの反射波があるのでしょうか。6号棟の場合は結局有効な反射波も回折波もないため、方向よりはブースターに頼っているのかもしれません。
いずれのお宅もアンテナ直近に屋外用のブースターは付けていません。恐らく我が家同様、アンテナボックスあたりにブースターを設置しているものと思われます。